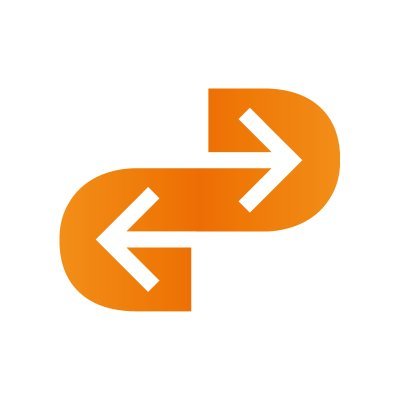初心者も簡単に投資が始められる!ソーシャルレンディングの概要と各社サービス比較
よく聞くけどいったいどういう類の投資なのか分からないという人も多いと思われる『ソーシャルレンディング』。
最安で1口1万円から、初心者でも非常に簡単に始められる投資です。
直接確認することが難しいこととデフォルトのリスクだけは要注意。
当サイトは、プロモーションを含みます。
※記事更新時の情報となります。申込期限や在庫状況により、提供を終了している場合があります。
また、お礼品の寄付金額も変更している場合があります。詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
投資の初心者でも簡単に資産運用できる「ソーシャルレンディング」というサービスが規模を拡大しています。株式投資やFXなどと異なり、誰でも簡単に投資できるのが魅力です。今回はこのソーシャルレンディングについてご紹介します。
ソーシャルレンディングとは
まずはソーシャルレンディングとはどんなサービスなのかを説明します。
ソーシャルレンディングはネット上でお金を貸し借りできるサービス
ソーシャルレンディングとは、お金を貸したい人と借りたい会社をマッチングするサービスです。そして投資家はこのソーシャルレンディングサービスを通してお金を貸し出し、金利という形で利益を得る仕組みになっています。
ソーシャルレンディングサービス業者は、資産運用をしたい個人投資家からお金を集めて、まとまった金額のお金を企業に融資します。個人投資家は少額から融資ができ、貸し出し金利に応じた利益を受け取ることができます。利益は毎月分配されるケースと、最終償還時にまとめて受け取るケースとがあります。
不特定多数の個人投資家からお金を集めるため、ソーシャルレンディングは融資型クラウドファンディングとも呼ばれます。
このサービスの大きな特徴は、貸し出す際の金利が高いことです。そのため投資家のリターンも高めになる傾向があります。
また、ソーシャルレンディングにはテーマがあることも特徴です。たとえば再生エネルギー事業や不動産、海外の個人など対象を絞って貸し出すスタイルになります。さらにサービス業者によって得意とするジャンルが異なり、不動産に特化したものやさまざまな事業に融資するものなどがあります。
投資家としては実際にソーシャルレンディングに投資して、利益が出るのかが気になるところです。
たとえばSBIソーシャルレンディングが2019年6月に発表した2018年度における決算内容を見ると、次のようになっています。
| 2018年 | 前年対比 | |
|---|---|---|
| 経常利益 | 17億5669万7000円 | 169%増加 |
| 匿名組合損益分配額 | 15億2,143万円 | 176%増加 |
このように順調に事業は拡大し、投資家に対する分配金も増加していることがわかります。
ソーシャルレンディングの法的整備
お金を貸すことに関しては、金融商品取引法や貸金業法といった法規制があります。そのためソーシャルレンディング事業者は、「第二種金融商品取引業者」と「貸金業者」のふたつの登録を行うことになります。
そのためソーシャルレンディングを利用する個人投資家は法規制に制限されることなく、お金を貸し出すことによる利益を得られる仕組みとなっています。
ソーシャルレンディングの仕組みとリスク
ソーシャルレンディングの仕組みは簡単です。まず融資を必要とする事業者が、どのような事業で資金を必要としているのかをソーシャルレンディングサービスのサイトに掲載します。そこに必要とする資金金額と金利が掲載されます。
投資家はそのような事業から好きなものを選び、一口いくらという形のお金を出資します。この時点で投資家は、サービス提供事業者と匿名組合契約というものを締結します。これは出資したお金をサービス事業者が運用し、そこで生じた利益を組合員に分配するというものです。そしてサービス事業者は融資する事業者と金銭消費貸借契約を締結します。
このふたつの契約によって法的に問題なく、個人投資家はお金を貸し出し、その金利を受け取ることができるというわけです。
ソーシャルレンディングは融資先が支払う金利と投資家に分配する金利との差額が手数料となるので、別途に手数料を支払うことはありません。
融資先に関してはソーシャルレンディングサービス事業者が審査をしますが、貸し倒れが皆無というわけではありません。つまり返済が不可能となった場合には、投資家には出資したお金が戻ることはないということです。
このようなリスクがあるために、金利水準は高めに設定されています。
ソーシャルレンディングの利益の出し方
ソーシャルレンディングサービスはいろんなテーマにカテゴリ分けして融資をしています。そのため、収益性や将来性が異なるいくつかのテーマに資金を分けることで、リスク分散ができます。
あとは事業内容をチェックして収益性を調べ、貸し倒れのリスクが極力少ない案件を選ぶようにするのがリスク回避のコツと言えます。
ソーシャルレンディングに関連した最近のニュース
ソーシャルレンディングに関してはいろんなニュースが配信されます。もっとも多いのは、どのような募集が開始されたのかということです。
太陽光発電事業者のファンドが募集開始(2020年2月7日)
これはSBIソーシャルレンディングが2020年2月10日から募集を開始するファンドのニュースです。
「SBISLメガソーラーブリッジローンファンド26号」というものですが、ソーシャルレンディングにおいてはこのようにファンド名が掲載されて投資家を募集します。
そしてこのファンドに関しては、募集期間が2月10日午前10:00から2月13日昼12:00までとなっています。
一口5万からで募集額は2億5,100万円と、かなり大口の案件であることがわかります。年利回りは6.0%と、ソーシャルレンディングのなかではさほど高くない数字になるので、リスクも比較的低いと考えられます。
運用期間は10カ月ほどとなり、出資金の返還はプロジェクトが終了した最終分配日となっています。
ソーシャルレンディングが急拡大(2020年1月4日)
調査会社「富士キメラ総研」によると、2019年のソーシャルレンディングの市場規模は推定で前年比25%増の1,600億円となり、さらに2020年も同程度の増加率が見込めるとのことです。
銀行預金ではほとんど金利がつかず、かといって株式投資のようなリスクのあるものには手を出しにくいことから、安定的に利益を生み出すソーシャルレンディングに個人投資家の注目が集まっているのが理由のようです。
ソーシャルレンディングのメリット
ソーシャルレンディングの大きなメリットは、投資経験に関係なく誰でもある程度の利益が見込めることです。
たとえば株式投資やFXなどは、投資経験などの差が運用利回りに大きく影響します。初心者の場合には、損失を出す可能性も高いものです。
その点、ソーシャルレンディングは基本的にデフォルト(融資を受ける事業者が経営破綻すること)の可能性が低く、損失を被るリスクも少ないという利点があります。また複数のファンドに資金を分散することで、損失リスクはさらに低下できます。
次に投資資金も少ないのがメリットと言えます。
ソーシャルレンディングはファンドの案件にもよりますが、SBIソーシャルレンディングの場合には一口1万円から募集するファンドがあります。これから投資を始めてみようという人にとって、敷居が低いというのが大きなメリットです。
ソーシャルレンディングのデメリット
ソーシャルレンディングの大きなデメリットとしては、最初から期待できる利益率が決まっていることが挙げられます。ファンドによって金利が決まっているので、それ以上の収益が期待できるということはありません。
この点は株式投資やFXのように、うまく波に乗れば大きな利益が期待できるということはないということです。そのため、短期間で資産を大きく増やすという夢を持つことはできません。
またソーシャルレンディングは通常のファンドとは異なり、満期になるまで資金を引き上げることができないのもデメリットとなります。
一般的な投資ファンドは、手数料がかかるものの、満期まで待つことなく途中で解約できます。急にお金が必要になった時には、ファンドを現金化できます。一方でソーシャルレンディングの場合には、お金を融資して事業に充てているので、途中で解約するわけにはいきません。そのため、生活費として充当する予定のない余裕資金で運用することが大切と言えます。
そしてもうひとつ、ソーシャルレンディングのファンドはどのような企業に融資されるのかがわからないようになっています。事業内容も詳細にわかるわけではないので、貸出先に関する情報はあまり得られない点がデメリットと言えるでしょう。
事業によっては返済が不可能となり、デフォルトとなることも皆無ではありません。そのため、おおまかな事業内容と金利の数字から、どのくらいのリスクがあるのかを推測するしかないというのが実情になります。
ソーシャルレンディングの各サービスの紹介
それでは実際にどのようなソーシャルレンディングサービスがあるのか、いくつかをご紹介します。
SBIソーシャルレンディング
SBIホールディングスの傘下となるソーシャルレンディングサービスです。貸付総額は2020年1月15日の時点で956億9,620万円、登録完了数は2020年1月末時点で45,143人となっています。利益は毎月分配されます。
ソーシャルレンディングはもともと中小企業による小口の融資案件が多いものですが、SBIソーシャルレンディングの場合には億を超える大型案件の募集が多いのが特徴です。
しかも募集を開始してからそれほど時間をかけずに、必要とされる投資上限金額に達する案件も少なくありません。
利回りは年に5%~7%ほどと控えめな数字ですが、貸し倒れが発生しても90%近い回収率で投資家の損失を最小限に抑えるという実績もあります。
2020年1月15日時点でのデフォルトした貸付元本は累計で183,822,417円です。
ファンドの種類は以下のとおりです。
・オーダーメード型
・常時募集型
maeno
日本で最初に誕生した老舗のソーシャルレンディング会社です。ファンドの運用利回りは年に5%~8%となっています。
ファンドの運用期間は最長36カ月と長いものから、わずか1カ月と短いものまで揃っています。ソーシャルレンディングの初心者であれば、最初は1カ月の運用ファンドを選ぶとよいかもしれません。
2020年2月時点の成立ローン総額は1,644億5,417万円、登録ユーザー数は87,887人となっています。デフォルト件数は0件、金額も0円となっていますが、延滞は割とあります。612件中で38件が延滞中であり、金額は85億9,600万ほどになります。元本回収率はほぼ0%に近い案件もあります。
扱うファンドの種類は以下のようになります。
・不動産担保ローン
・事業用投資資金
・太陽光発電
・海外ローン債権
・その他
OwnersBook
東証マザーズ上場企業の「ロードスターキャピタル株式会社」が運営するソーシャルレンディングサービスです。提供するすべてのファンド案件には国内不動産担保がついている、不動産に特化したサービスであるのが特徴です。年間利回りは2%~6%という成績になっています。
投資資金は一口が1万円からとなります。特定の不動産(マンションなど)を保有する企業への不動産担保ローンに出資する形です。募集は先着順と抽選型と2種類があります。
2019年第3四半期における累積投資金額は139億800万円、会員数は21,903人となっています。デフォルトに関する情報は公式サイトには記載されていません。
扱うファンドは不動産案件のみです。
funds
投資金額がわずか1円から、1円単位で参加できるのが特徴のソーシャルレンディングサービスです。運用実際は年3%前後と決して多くはありませんが、手軽に投資できる利点があります。
担保がない案件がほとんどですが、融資先は上場企業が多く、デフォルト件数もないので100%回収されています。投資期間は1カ月から12カ月と比較的短期になっています。ただし募集を開始するとわずかな時間で終了してしまうのが難点と言えます。
fundsも公式サイトにはデフォルトに関する情報は記載されていません。扱っているファンドは次の2種類です。
・ローン型
・不動産型
ソーシャルレンディングの比較
| 貸付総額 | 登録数 | 利回り | 運用期間 | |
|---|---|---|---|---|
| SBIソーシャルレンディング | 956億9,620万円 | 45,143人 | 5%~7% | 9カ月〜36カ月 |
| maeno | 1,644億5,417万円 | 87,887人 | 5%~8% | 1カ月〜36カ月 |
| OwnersBook | 139億800万円 | 21,903人 | 2%~6% | 1カ月〜20カ月 |
| funds | 不明 | 不明 | 3%前後 | 4カ月〜12カ月 |
まとめ
ソーシャルレンディングはお金を貸すことで得る金利が利益となる投資手法です。手間がかからず、わずかな資金から始めることができるのがメリットと言えます。
関連するキーワード
 ふるさと納税アノニマス
ふるさと納税アノニマス
某保険会社勤務。ふるさと納税自分でも行なうし、お客さんにもすすめたりしています。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング